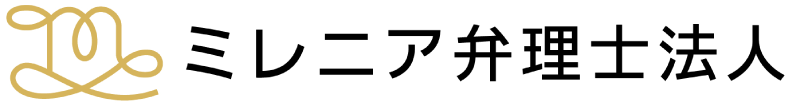特許の出し方|失敗しない5ステップ【初心者向け】
特許の出し方が分からず不安…という方へ。この記事では、初心者でも迷わないように、特許の出し方を5つのステップでやさしく解説します。まずは「何が特許になるのか」を理解し、出願の準備とタイミングを押さえるのがコツです。
Step1:まずは「特許になるか」を見極める(特許の出し方の出発点)
特許にできるのは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」。つまり技術の仕組みが必要です。例:化粧品の新しい配合、日用品、装置の改良構造、装置の製造方法、プログラムの処理方法、ビジネス特許など。
一方、「単なるアイデア」「デザイン」「ルール」は特許ではなく、商標・意匠・著作権など別制度の対象です。
(関連記事)特許と実用新案の違いとは?初心者にもわかりやすく解説
Step2:アイデアを具体化する(発明提案書を作る)
- どんな課題を解決したい?
- どんな構成・手段で実現?
- どんな効果・利点がある?
化学・材料系では比較データや実験結果があると審査で有利。特許の出し方でつまずきやすいのが「具体化不足」です。
Step3:出願前に公開しない(新規性喪失の回避)
学会発表・展示会・SNS投稿などで出願前に技術を公開してしまうと、新規性喪失により特許が取れなくなるおそれがあります。
「後で出せばいいや」と思って公開してしまうと、他社に真似されたり、自分の発明が特許にならなかったりするリスクがあります。
出願の前に必ず専門家へ相談し、公開予定の資料を確認しましょう。
(関連記事)新規性とは?特許が取れなくなる理由と回避策をわかりやすく解説
Step4:特許出願を行う(明細書・クレームが肝)
- 特許請求の範囲(権利の核心)
- 明細書(発明の詳細)
- 図面(必要に応じて)
- 要約書
オンラインでの自己出願も可能ですが、明細書とクレーム作成は専門性が高いため、弁理士に依頼すると結果が安定します。その後、出願から約1年半で公開されます。続いて、審査請求をすることにより、審査開始されます。
Step5:審査・登録までの流れ
新規性・進歩性・先行特許との重複を審査。拒絶理由通知がきたら、意見書や補正書で反論・補正します。登録後は最長20年保護。
特許庁の印紙代の目安
以下は、特許庁へ支払う印紙代です。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 出願手数料 | 約14,000円(電子出願) |
| 審査請求料 | 約142,000円〜(請求項1,請求項数で変動) |
| 登録料 | 年数による(初年度約2万円〜) |
弁理士費用は別途必要です。自部で出願書類を作成することも可能です。とはいえ、出願の質が結果を左右するため、長期的にはコスパ良好です。
まとめ:特許の出し方は「準備」と「タイミング」
技術の具体化、データの準備、公開前の出願。ここを押さえれば、特許の出し方は難しくありません。迷ったら早めに専門家へ。
関連リンク
ミレニア弁理士法人より
化学・バイオ・半導体の特許に強み。機械・電気電子・プログラムも対応。
先行技術調査、侵害・無効化調査も可能です。お気軽にお問い合わせください。