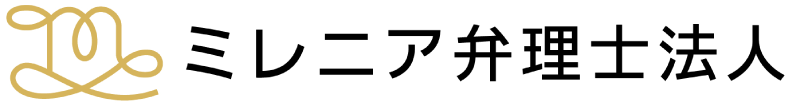「せっかく良いアイデアを思いついたのに、似たような特許がすでに出ていた」
そんな経験をしたことはありませんか?
特許出願を行う前には、必ず「先行技術調査」を行うことが大切です。これは、すでに出願・公開されている技術(=先行技術)を調べる作業のこと。出願の可否を判断したり、拒絶されるリスクを減らしたりするうえで欠かせないステップです。
1.なぜ先行技術調査が必要なのか?
まず、なぜ調査が必要なのかを整理してみましょう。特許出願は審査で「新規性・進歩性」が厳しくチェックされます。つまり、すでに同じような技術が存在すれば、原則として特許にはなりません。
このため、出願の前に「似た発明がないか」「どこを差別化すれば通りやすいか」を確認しておくことが重要になります。調査をしておくと、無駄な出願を避けられるだけでなく、クレームの書き方や発明の方向性を早い段階で整理できます。とくに開発初期に調べておくと、その後の研究テーマ選定にも役立ちます。
2.先行技術調査とは?
「先行技術調査」とは、過去に出願・公開された特許文献や学術文献を検索し、
自分の発明と似た技術がすでに存在しないかを確認する作業です。
日本では、特許庁が提供する無料データベース「J-PlatPat(ジェイプラットパット)」を使えば、
誰でも簡単に検索できます。
また、Google Patentsなど海外の公開情報も活用すれば、
世界的な技術動向を把握することも可能です。
3.自分でできる簡易調査の方法
先行技術調査というと「難しそう」と感じる方も多いですが、実は、ある程度の範囲なら自分でも調べられます。ここでは、最初に試してみたい4つの方法をご紹介します。
(1)キーワード検索
まずは、思いつく単語を組み合わせて検索してみましょう。たとえば「粘着剤」「生分解性」「マイクロカプセル」「アクリル系」など、材料名・構造・用途などをキーワードにします。
ただし、注意したいのは言葉のゆれです。同じ技術でも「接着剤」「感圧接着剤」「Pressure-sensitive adhesive」など、表記が異なることがあります。日本語と英語の両方を試すのがおすすめです。
(2)出願人や発明者で検索
競合企業や研究機関の出願状況を把握するのも効果的です。たとえば「花王」「資生堂」「東京大学」など、特定の出願人名で検索すると、業界の動向や注力分野が見えてきます。類似企業やグループ会社名の表記揺れにも気を付けましょう。
(3)分類検索(IPC・FI・Fターム)
特許文献には、内容に応じた分類番号(IPCやFI、Fターム)が付けられています。言葉が異なっても同じ分類に属していれば、技術の分野は似ています。まずは1件、核心に近い公報を見つけ、その文献に付けられた分類をクリックして「同じ分類の他の公報」を芋づる式に調べるのがコツです。
(4)引用・被引用をたどる
特許文献には「引用文献」「被引用文献」が示されています。ある技術を引用している文献は、より新しい改良技術である場合が多いため、引用関係をたどることで、技術の進化の流れを把握できます。
4.調査で見落としを防ぐコツ
調査では、「見落とし」が最大のリスクです。少し工夫するだけで、精度を大きく上げることができます。
- 課題・効果・用途の観点で広く拾う:同じ材料を使っていても、目的が違えば別の発明として扱われる場合がある。
- 表記揺れを意識する:microcapsule / microencapsulation / マイクロカプセルなど、少し違う単語でも同じ意味になることがある。
- 最近の文献までチェック:審査で挙げられるのは“出願時点で公開済み”の文献です。最新情報まで確認しておきましょう。
- 類似用途を探す:まったく同じ用途でなくても、技術構成が共通している場合は要注意です。
5.専門家に依頼するメリット
もちろん、自分で調査するのは限界もあります。特に出願を本格的に検討している場合は、弁理士など専門家に依頼するのが安心です。
専門家に依頼するメリットは、主に3つあります。
- 広い視点での調査ができる。
自分では思いつかないキーワードや分類を用い、抜け漏れを減らせます。 - 拒絶理由を想定できる。
審査で引用されそうな文献を事前に把握し、クレームの差別化を検討できます。 - 将来の出願戦略につながる。
関連する意匠・商標、改良発明や分割出願を見据えた設計が可能です。
とくに、化学や材料系など表現の幅が広い分野では、
専門家の目で俯瞰的に調査することが大切です。
6.まとめ
特許出願は、出すこと自体が目的ではありません。本当に守るべき「差別化ポイント」を見極めてこそ、知的財産として価値が生まれます。
そのための第一歩が、先行技術調査です。出願前に調べておくことで、拒絶を避け、より強い特許を取得する可能性が高まります。
ミレニア弁理士法人では、出願前調査から戦略的なクレーム作成までを一貫してサポートしています。
化学、化粧品、半導体、装置、プログラム分野など、幅広い分野に対応可能です。
発明を「守る」だけでなく、「活かす」ための知財戦略を一緒に考えましょう。
関連リンク: