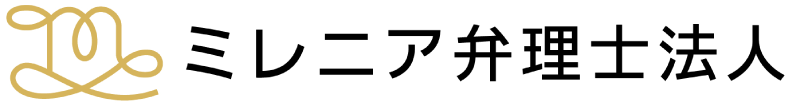~制度の違いと費用の目安~
最近、こんなご相談を受けました。
確かに、特許と実用新案はどちらも技術的アイデアを守るための制度ですが、仕組みも費用も大きく異なります。違いを知らないまま出願してしまうと、「思っていたのと違った…」という結果になりかねません。
「制度が二つあるけど、どう違うんですか?」
「費用ってどれくらいかかるんでしょうか?」
この記事では、実際の相談事例を交えながら、制度の違いと費用の目安をわかりやすく整理します。これから知財戦略を検討される方の参考になれば幸いです。
🧭 制度の違い:特許 vs 実用新案
まずは基本的な仕組みの違いを整理します。
| 項目 | 特許制度 | 実用新案制度 |
| 🔍 審査の有無 | 実体審査あり(新規性・進歩性・産業上利用可能性) | 審査なし(形式審査のみ) |
| 🛡️ 保護対象 | 発明(方法、構造、物質、ソフトウェアなど) | 物品の形状・構造・組み合わせに限定 |
| ⏳ 権利化までの期間 | 通常1~2年(早期審査制度あり) | 通常2~6か月(迅速に登録可能) |
| 📅 存続期間 | 出願日から最長20年 | 出願日から最長10年 |
| ⚖️ 権利の強さ | 強い(審査済みのため権利行使が安定) | 弱い(技術評価書が必要、行使に注意) |
| 📈 ビジネス適性 | 長期的な技術保護、模倣防止に有効 | 短期的な牽制、スピード重視の製品に有効 |
💰 費用の違い(概算・請求項5個の場合)
続いて、気になる費用面の比較です。
| 費用項目 | 特許制度(請求項5個) | 実用新案制度(請求項5個) |
| 出願料 | 約14,000円 | 約14,000円 |
| 審査請求料 | 約158,000円 | 不要 |
| 登録料(1~3年分) | 約17,400円 | 約7,800円 |
| 技術評価書請求(任意) | 不要 | 約47,000円(権利行使時に必要) |
| 弁理士費用(目安) | 約25~50万円 | 約20~30万円 |
| 合計(庁費用のみ) | 約189,400円以上 | 約21,800円+技術評価書費用 |
※実際の費用は請求項数や出願方法によって増減します。
🧮 正確な費用はJPOの自動計算ページで
上記はあくまで概算です。実際の費用は、請求項数や出願方法(電子出願か書面出願か)によって変動します。
特許庁(JPO)の公式サイトでは、庁費用を自動計算できる便利なページが公開されています。
▶︎ 特許庁:手数料自動計算ページ
📖 実際の相談事例
今回ご相談くださった企業様は、新しい製品を短期間で市場投入する計画をお持ちでした。
「模倣品がすぐに出るのではないか」と心配されていましたが、長期的な権利保護までは必要とされていませんでした。
検討の結果、実用新案を選択。
理由は以下の通りです:
- 出願から数か月で登録され、早く「登録済み」という事実を示せる
- 特許よりも庁費用・弁理士費用を抑えられる
- 取引先へのアピール材料になる(「知的財産で守っている」という安心感)
権利行使は想定していませんが、ビジネス上は「実用新案登録済」というだけで信頼感が増し、十分に役立つと判断されました。
このように、制度の選択は「技術の内容」だけでなく「ビジネス戦略」によっても変わります。
✨ まとめ
- 特許制度:長期的に技術を強力に守りたい場合におすすめ
- 実用新案制度:スピード重視・費用を抑えたい場合に有効
- 制度の選択は、技術そのものの特徴 × 事業戦略 によって決まる
- 実用新案は権利の強さでは劣るが、登録の速さや費用の安さでビジネスに活用できる
👩💼 最後に
知財制度は一見複雑ですが、実際のビジネスに照らし合わせると「どちらが合うか」は意外と明確になります。
- 長期的に守りたい大きな発明 → 特許
- 製品寿命が短くスピードを重視したい → 実用新案
迷われる方は、ぜひ専門家に相談してみてください。
最適な制度を選ぶことが、知財をビジネスに活かす第一歩です。
弊所では、化学、バイオ、半導体関連の特許出願を主に、機械、電気電子、プログラム関連の特許出願もしております。
先行技術調査、侵害調査、無効化調査も可能です。
お気軽にお問い合わせください。