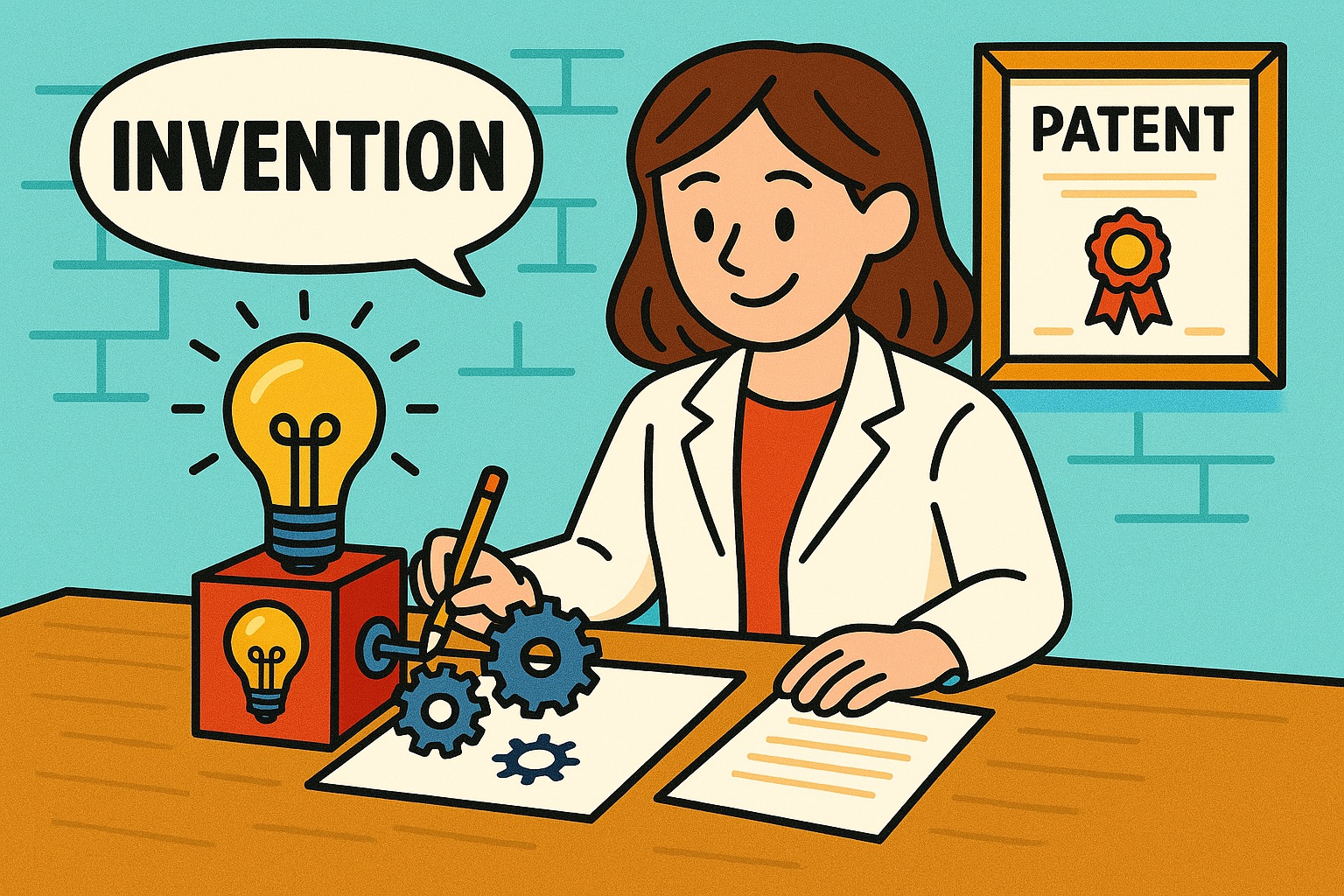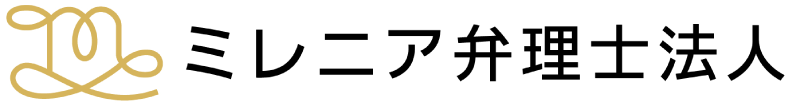「特許を出願すればすぐ守れるのか?」
これは中小企業の経営者や研究者からよく聞かれる質問です。実際には、特許 出願 守れるのは特許査定後であり、それまでの間には公開制度や補償金請求権といった段階があります。
中小企業の経営者さんや特許出願を考えている人からよく聞かれる質問の一つが、
「特許を出願したらすぐに独占できるんですか?」
というものです。
答えは「いいえ」。実は出願から特許査定が出るまでには時間がかかり、その間は思っているほど強い権利はありません。では、その間に出願人はどんな立場に置かれているのか、順を追って見ていきましょう。
特許出願 守れるのはいつから? 出願から1年半は非公開
特許出願をすると、その内容はすぐには公開されません。原則として「出願日から1年6か月」が経過した時点で、特許庁によって公開されます。これを「出願公開制度」と呼びます(特許庁公式サイト|出願公開制度)。
公開されると、誰でもインターネットでその明細書を読むことができるようになります。競合企業も例外ではありません。研究者が文献検索でチェックできるのもこの仕組みのおかげです。
この制度にはメリットとデメリットがあります。
- メリット:技術が公開されることで、重複研究や同じ発明の再出願が防げる。技術情報が社会全体に循環する。
- デメリット:自社の戦略をライバルに知られてしまう。
つまり、出願から公開までの1年半は、ある意味「秘密の期間」です。この間に製品化や事業準備を一気に進めることが重要になります。
特許出願ですぐ守れるわけではない理由と補償金請求
では、公開されるまでは何の効力もないのか?というと、そうではありません。
出願公開後には「補償金請求権」という仕組みがあります。これは、公開された出願内容と同じ発明を他社が実施していた場合に、特許が成立した後にさかのぼって補償金を請求できる権利です。
ただし、注意点があります。
- 補償金はあくまで「通常の実施料相当額」が基準。損害賠償のように大きな金額を請求できるわけではない。
- 実際に請求するには、その出願が最終的に特許査定されることが前提。拒絶されてしまえば、補償金は請求できない。
- 相手方に出願が公開されている事実を知らせておく必要がある。
つまり、補償金請求権は「権利が成立するまでの間の仮の効力」であり、実務上は交渉のカードとして使われることが多いのです。
特許査定後に得られる本当の効力
特許庁の審査を経て、出願が認められると「特許権」が発生します。ここではじめて、強い独占排他権が与えられます。
特許権者は、原則として他人にその発明を無断で実施させない権利を持ちます。ここで登場するのが「専用実施権」と「通常実施権」です。
専用実施権と通常実施権
- 専用実施権
特許権者が第三者に設定できる権利。設定された人以外は誰もその発明を実施できません。もちろん特許権者自身も実施できなくなる強力なライセンスです。独占的に使用したい場合に用いられます。登録が必要です。 - 通常実施権
こちらはもっと柔軟なライセンス契約。複数の相手に同時に許諾でき、特許権者も自分で実施可能です。契約すれば効力が発生し、登録は必須ではありません。 - 独占的通常実施権
実務上よく用いられる形態です。通常実施権の一種ですが、契約によって「特許権者も実施できない」という条件を付けることができます。専用実施権に近いですが、契約ベースなので柔軟に設定できます。
このように、特許の「使わせ方」にはいくつかのレベルがあり、企業の戦略に応じて選ぶことが大切です。
中小企業が知っておくべきポイント
- 出願=すぐ独占ではない
実際に独占的に守れるのは特許査定後。出願中の段階ではあくまで「仮の効力」にすぎません。 - 公開までの1年半はチャンス期間
ライバルがまだ出願内容を知らない間に、製品化・販売準備を進めましょう。 - 補償金請求権は交渉カード
実務的には、ライバルに「こちらの技術を使っているなら、後で補償金を払ってもらいますよ」と伝える抑止力になります。 - ライセンスの使い分けが重要
- 独占させたいなら専用実施権や独占的通常実施権
- 幅広くライセンス収入を得たいなら通常実施権
自社のビジネスモデルに合わせて設計する必要があります。
まとめ
結論として、特許 出願 守れるのは特許査定後であり、それまでは補償金請求権という限定的な効力しかありません。
特許を出願したらすぐに守れると思われがちですが、実際には出願から公開、そして審査を経て特許査定に至るまでには時間がかかります。その間は補償金請求権という限定的な効力しかなく、真に強い権利を持てるのは特許成立後です。
また、成立後にどうライセンスを組むかによって、その特許が会社の収益に結びつくかどうかが決まります。専用実施権、通常実施権、独占的通常実施権をうまく使い分けることが重要です。
知財は単なる法律知識ではなく、企業経営そのものに直結する戦略ツールです。特許制度の仕組みを正しく理解し、自社の強みを最大限に活かす形で活用していただければと思います。
ミレニア弁理士法人では、化学、バイオ、半導体関連の特許出願を主に、機械、電気電子、プログラム関連の特許出願もしております。
先行技術調査、侵害調査、無効化調査も可能です。
お気軽にお問い合わせください。
参考リンク