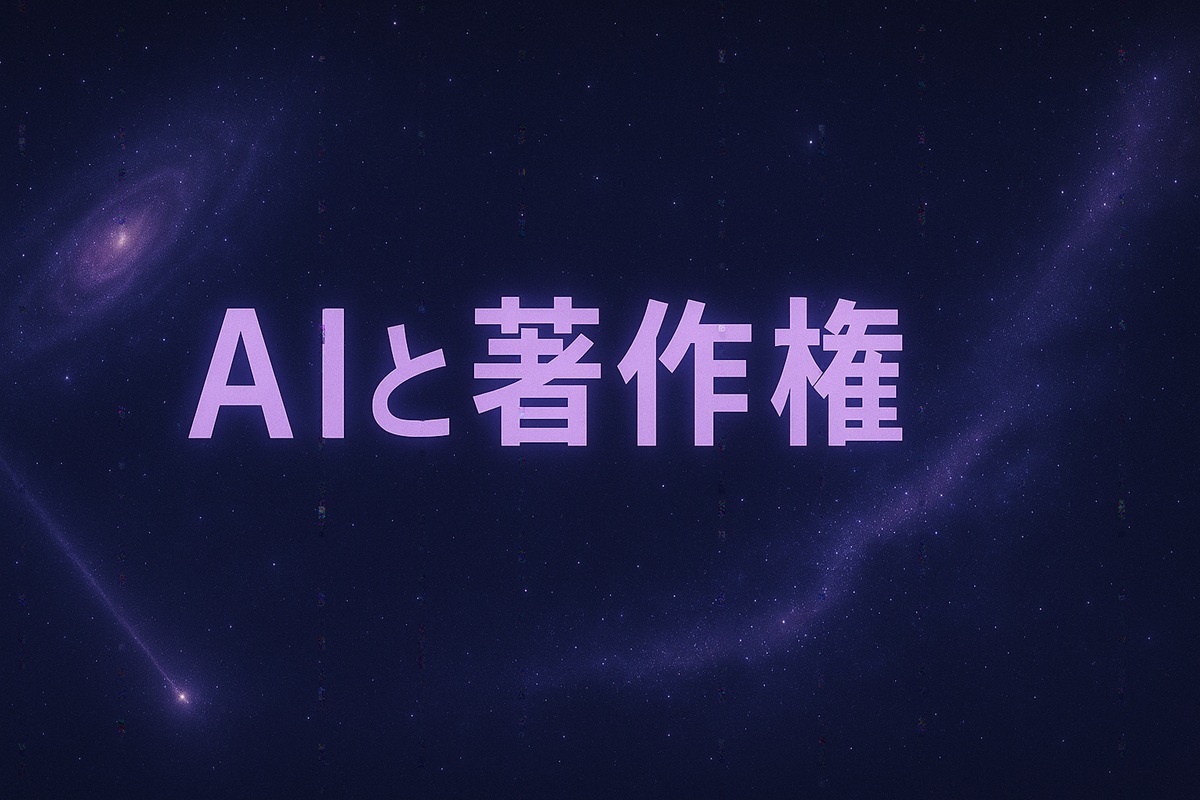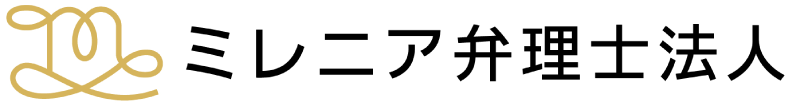はじめに
ChatGPTや画像生成AIなど、生成AIの利用は急速に広がっています。
しかし「AIが作った文章や画像、プログラムに著作権はあるのか?」という疑問は、まだ答えが明確ではありません。
日本では裁判例がなく、実務家も手探りの状態です。本記事では、日本の制度を解説しつつ、米国での事例を紹介し、今後の展望を考えてみたいと思います。
日本の著作権法とAI生成物
日本の著作権法第2条は「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義しています。
そして「著作者」とは「著作物を創作した者」であり、ここでいう「者」は自然人、すなわち人間を指します。
このため、AIが完全に自律的に作成した成果物には、著作権は認められません。
著作権を持つ主体は人間に限られるからです。
もっとも、AIの利用過程において人間が「指示」「選択」「修正」「構成」などに十分関与していれば、その人の著作物と認められる可能性があります。
ただし「関与の程度」がどこまで必要なのか、現時点で明確な基準はありません。
米国における代表的な事例
DABUS事件(発明の著者問題)
AI「DABUS」が考案者とされた特許出願が各国で行われましたが、米国特許商標庁(USPTO)は「発明者は自然人に限られる」として却下しました。
これは特許の話ですが、「創作者は人間に限られる」という原則が著作権にも貫かれていることを示すものです。
Kristina Kashtanova事件(AIアートと著作権)
米国では、Kashtanova氏がAI「Midjourney」を使って制作したコミック「Zarya of the Dawn」に著作権登録を申請しました。
米著作権局は「ストーリーや編集構成など人間が作った部分」については著作権を認めました。しかし、「AIが自動生成した画像」については著作権を否定しました。
つまり「人間の創作的寄与がある部分だけが保護対象になる」とされたのです。
Thaler v. Perlmutter判決
米国のStephen Thaler氏が「Creativity Machine」というAIに生成させた画像「A Recent Entrance to Paradise」の著作権登録を試みました。
米著作権局は「AIのみで作成された作品には著作権を認めない」と判断しました。
この事例は「AI単独の成果には保護なし」という原則を明確に示したものとして注目されています。
企業・研究者が注意すべきポイント
生成AIをビジネスに使う場合、次のような注意が必要です。
- 利用規約の確認
AIサービスごとに、生成物の著作権や利用条件が異なります。商業利用可能か、再配布可能かを必ず確認しましょう。 - 著作権侵害のリスク
AIが学習データとして既存の著作物を利用している場合、生成物が既存作品に類似する可能性があります。結果的に他人の著作権を侵害するおそれがあります。 - 人間の関与を明確にする
AIを使った創作では、「誰がどの部分を作ったか」を記録に残しておくことが重要です。後々、著作権の有無を判断する上での証拠になります。
今後の展望
日本ではまだ裁判例が存在しないため、今後の司法判断次第で大きく変わる可能性があります。
とくに「人間の関与がどの程度あれば著作物と認められるのか」という点が最大の争点になるでしょう。
企業にとっては、AIの利用が避けられない時代に入っています。
そのため早めに「AI生成物の利用ルール」や「著作権チェック体制」を整備しておくことが、リスクを避ける上で大切です。
まとめ
- 日本法では著作者は人間に限られ、AI単独の成果物には著作権は認められない。
- 米国の事例では「人間が創作的に関与した部分のみ」保護対象とされている。
- 企業がAIを利用する際には、利用規約の確認・侵害リスク管理・人間の関与の記録が不可欠。
生成AIと著作権は、今後のビジネスに大きな影響を与えるテーマです。
最新の議論や制度改正を注視しつつ、リスクを踏まえた活用を心がける必要があります。
ミレニア弁理士法人からのお知らせ
ミレニア弁理士法人では、化学、バイオ、半導体関連の特許出願を主に、機械、電気電子、プログラム関連の特許出願も行っております。
先行技術調査、侵害調査、無効化調査に加え、著作権や不正競争防止法、生成AI利用に関するご相談も可能です。
お気軽にお問い合わせください。