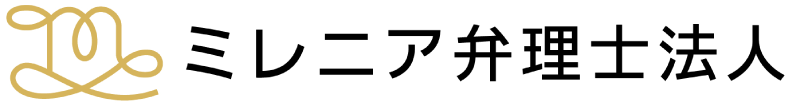学会シーズンになると、研究成果を社会に発信する場面が増えます。
しかし同時に、「新規性喪失の例外規定」に関する相談が企業や研究者から多く寄せられます。
例えば──
- 「学会発表を予定しているが、特許出願はまだ間に合っていない」
- 「予稿集が公開されると特許に影響するのでは?」
- 「海外出願を予定しているが、発表を優先しても大丈夫か?」
研究成果の発表は社会的に意義深い一方で、特許の新規性を失わせる危険性を伴います。
そこで重要になるのが 新規性喪失の例外規定 です。
学会発表と特許出願 ― 新規性喪失の例外規定の重要性
近年、大学や企業における研究成果の発信は活発化しており、学会発表・展示会・論文投稿・プレスリリースなどの機会が増えています。
一方で、成果を特許にして事業化したいというニーズも強まっています。
ここでしばしば問題になるのが、**「発表と特許出願の順序が逆転してしまう」**ケースです。
本稿では、研究成果を公表した場合に適用できる新規性喪失の例外規定について、実務上の留意点を整理します。
1.特許の新規性と新規性喪失のリスク
特許法第29条1項では、
「産業上利用することができる発明であって、新規性および進歩性を有するもの」
は特許を受けることができると規定されています。
ここでいう「新規性」とは、出願前に発明が公然知られていないことを意味します。
- 学会発表
- 展示会での公開
- 論文掲載
- インターネットでの情報発信
これらはいずれも「公然知られた行為」に該当します。そのため、出願前に発表すると自己の行為であっても原則として新規性を喪失し、特許要件を満たさなくなります。
2. 新規性喪失の例外規定の概要と要件
もっとも、研究者や企業活動で成果を全く公開できないのは非現実的です。
そのため特許法第30条は、一定の要件のもとで「自己の行為による公表」であれば新規性を失わなかったものとみなす規定を設けています(特許庁|https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/tokkyogaiyo/jirei/30.html)。
主な要件
- 自己の行為による公表
出願人自身またはその同意を得た者が発表した場合。典型例は学会発表・展示会出品・論文発表・Web開示。 - 出願までの期間
公表から1年以内に特許出願する必要あり(特許法30条2項)。 - 例外規定の手続き
出願時に「新規性喪失例外適用願」を提出し、その後証明書類を整える必要があります。証拠としては学会予稿集・展示会パンフレット・発表プログラムなどが利用されます。
3. 新規性喪失の例外規定で注意すべき実務ケース
(1) 学会予稿集の公開時期
学会発表そのものよりも、予稿集やアブストラクトの事前公開がリスクです。
発表日より数週間~数か月前にWeb公開されることがあり、その公開日が新規性喪失の起算点となります。
(2) 複数人による発表・共同研究
大学と企業の共同研究では、発表者が大学側でも特許出願は企業名義になることがあります。
この場合「自己の行為による公表」に当たるかが問題になります。
共同発明関係が認められる場合は適用されますが、そうでない場合は例外の対象外になる可能性があります。
(3) 海外出願との関係
海外では日本のような救済規定が整備されていない国もあります。
- 米国:1年のグレースピリオドあり
- 欧州・中国:例外の範囲が限定的
したがってグローバルに特許を取得する場合は、発表前に出願を完了させるのが鉄則です。
(参考:WIPO|Grace Period)
特に展示会では、説明担当者のちょっとした発言が新規性喪失につながることもあります。詳しくは、展示会での知財リスクとオープンクローズ戦略 の記事をご覧ください。
4. 新規性喪失の例外規定に必要な証明書類
例外規定を利用するには、証拠資料を揃えることが必須です。
例えば学会予稿集の場合は以下を記載した証明書を準備します。
- 公開の事実
- 発行日
- 刊行物名
- 公開者
- 公開発明の内容
- 権利承継等の事実
- 発明者名
- 公開時に特許を受ける権利を持つ者
- 特許出願人
- 公開者との関係
- 権利承継の有無
これらを明確にしておくことで、後日の無効審判で争われにくくなります。
5. 実務上の戦略的対応
結論として、以下の3点が重要です。
- 原則は発表前に出願
例外規定はあくまで救済措置。海外出願や証拠集めの難しさを考慮すれば、発表前の出願が基本方針です。 - 共同研究では早めの調整
大学・企業間で発表計画と出願計画をすり合わせ、予稿公開日を逆算してスケジュールを組む必要があります。 - 例外規定を使う場合は証拠確保
学会プログラムや公開日時を確実に保存しておくことが、手続成功の鍵です。
6. まとめ
学会発表や展示会での発表は、研究成果を広く社会に還元するために不可欠です。
しかし、特許の観点からは常にリスクを伴います。
- 国内出願なら新規性喪失例外規定を利用可能
- 海外展開を狙うなら発表前の出願が鉄則
- 共同研究では関係者間の調整が必須
特許のタイミング調整は研究者だけでは判断が難しいため、早い段階で知財専門家と相談することをお勧めします。